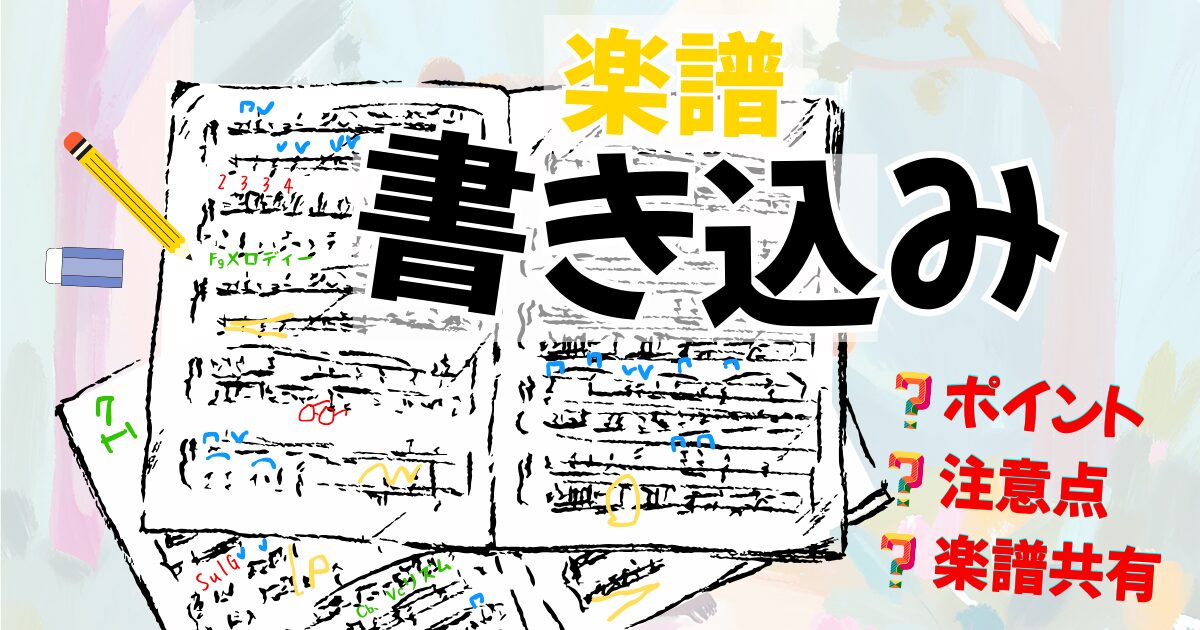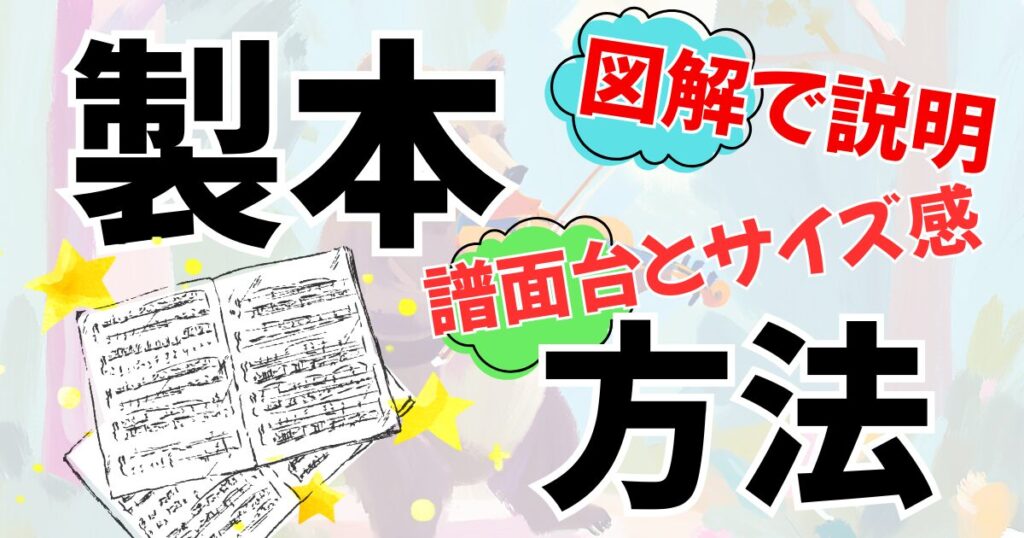楽譜への書き込みは、教科書のマーキングやノートへのメモに似ています。
指揮者の指示、他パートの動き、そして自分へのヒント——限られたスペースに必要な情報を整理して書き込むには、経験とスキルも求められます。
今回は、弦楽器奏者がよく書き込む内容から、楽譜を共有するときの注意点、書き込みの心得まで、実例とともにご紹介します!
楽譜に書き込むこと
1. ボウイング
パート内で統一することで、見た目も音も揃いやすくなります。
2. 小節番号や練習番号
印刷によっては見づらかったり、抜けていることも。
自分でふっておくと、指示のやりとりがスムーズになります。
3. 指番号やポジション
ポジション移動の起点や「SulG」の他にも、運指番号を書いておくと難所の対策になります。

4. 弓の位置
弦楽器の場合、「元弓」「中弓」「先弓」「全弓」など、弓を使う位置を揃えます。
5. 指揮者の指示
指揮者からは、強弱やテンポの他、フレージングや音色のイメージなど幅広い指示を受けます。
6. 参照すべき他パート
「クラリネットに合わせて入る」「ヴィオラと一緒に動く」など、他パートを意識してアンサンブル力をアップしましょう。

7. 強調
見落としがちな音楽記号や、演奏が足りない箇所は、目立つようにしておきましょう。
8.削除・追加・変更
指揮者の判断で「ここはボウイングを変更する」「ここはリットを追加する」など、楽譜と異なる解釈がある場合に。
9. めがねマーク
指揮者をしっかり見るべきタイミングにこのマークを書き込みます。
「rit.」や「G.P.」の箇所など。


書き込みにおすすめのペンを紹介するよ!
- 鉛筆シャープ(KOKUYO)
➢ 鉛筆のような書きごこち
➢ 折れにくく書きやすい
➢ 太字だから読みやすい
➢ 鉛筆風の六角軸で持ちやすい
| 本体カラー | 替え芯 | 字の太さ(mm) |
|---|---|---|
| 白 | 2B、B、HB | 0.3、0.5、0.7、 0.9、1.3 |
| 黒 | 2B、B、HB | 0.3、0.5、0.7、 0.9、1.3 |
※ 1.3 のみ赤芯あり
- 鉛筆シャープ・TypeM(KOKUYO)
➢ 鉛筆のような書きごこち
➢ 落ち着いたダークトーンのボディ
➢ ビジネスシーンにも
➢ すべりにくくフィット感のあるラバーグリップ
➢ 金属クリップ付き
| 本体カラー | 替え芯 | 字の太さ(mm) |
|---|---|---|
| 青 | 2B、B、HB | 0.7 |
| 赤 | 2B、B、HB | 0.9 |
| 緑 | 2B、B、HB | 1.3 |
※ 1.3 のみ赤芯あり
《楽譜を共有》よくあるトラブルと対処法
弦楽器は、プルト(譜面台)で楽譜を使用します。
団で楽譜の用意が無い場合は、2人のうちどちらかの個人楽譜を共有することになります。
楽譜の書き込みがトラブルの種にならないよう、次のことを参考にしてください。
📝 書き込みに個人差がある
どのような情報を楽譜に書き込むかは、個人差があります。
共有する楽譜に、自分にとって必要な情報が十分に書かれていないことも。
■解決策:
・プルト内で書き込みの方針を決める(どこまで書くか、どんな記号を使うかなど)。
・お互いの書き込みを尊重する。
📝 個人的な指番号が書かれている
一人の楽譜に書かれた指番号(運指)が、もう一人にとっては弾きにくかったり、違和感があることがあります。
■解決策:
・運指が身についたら、なるべく削除する。
・書き込む際は、同じプルトの相手に一言確認しておくと安心です。
・色分けや上下分けで区別する。
📝 共有しない人の楽譜に書き込みができない
合奏中に使わない方の楽譜には、書き込みがされないと、個人練習で困ることがあります。
急遽、使う楽譜を交換する必要が起きた時も、対応ができなくなってしまいます。
■解決策:
・共有の楽譜に書き込むタイミングで、自分の楽譜にも書き込んでおきましょう。
・休憩中に書き写すのも◎
📝(自分の楽譜じゃないから)書き込みづらい
同じプルトの相手の楽譜に書き込むのは気が引けてしまい、必要な情報を共有できないことがあります。
解決策:
・「お互いに自由に書き込んでOK」というルールを共有しておくと◎
・書き込み担当をどちらかに決めておくのもスムーズです。
📝 字が読みにくい・小さすぎる
雑な書き込みや細かすぎる字が読みにくく、合奏中に困る原因になります。
解決策:
・書き込みは相手にも伝わるように、はっきり・ていねい・大きめに書くことを意識しましょう。

合奏中は走り書きになっちゃうから、家で清書してるよ!
書き込みの心得
| 1.簡潔に書く | 記号や略語を活用しつつ、見やすさ優先で! |
| 2. 鉛筆・消せるペンを使用する | 修正・消去しやすい筆記具を使いましょう。 芯は濃いもの(2Bなど)がおすすめ。 |
| 3. 色は使いすぎない | 黒を基本に、要注意の部分のみ色を使うのも◎ |
| 4. 指揮者の意図を反映させる | 書き込みは単なるメモではなく、音楽づくりの共通理解のためのもの。 |
| 5. 指示は取捨、変換して書き込む | 指示の本質を理解したうえで取捨し、自分の言葉や分かりやすい記号に置き換えましょう。 |
| 6. 書き込むタイミングを読む | 演奏を止めている間、休符の間、休憩時間など。 原則、書き込みより演奏が優先です。 |
| 7. 音をイメージできる書き込みをする | 音楽記号でなく、情景や感情で指示は、自分なりに解釈して音楽記号に落とし込むのも◎。 |

「大草原に風が吹くように」「悲しいだけじゃなく懐かしさを含めて」とか。
まとめ
書き込みは「自分のため」だけではなく、「パート全体のため」「曲のため」でもあります。
丁寧な書き込みが、パートの一体感や演奏の仕上がりを高め、ケアレスミスも防止にもつながります。

色々な人の書き込みに触れて、書き込みスキルを磨こう!