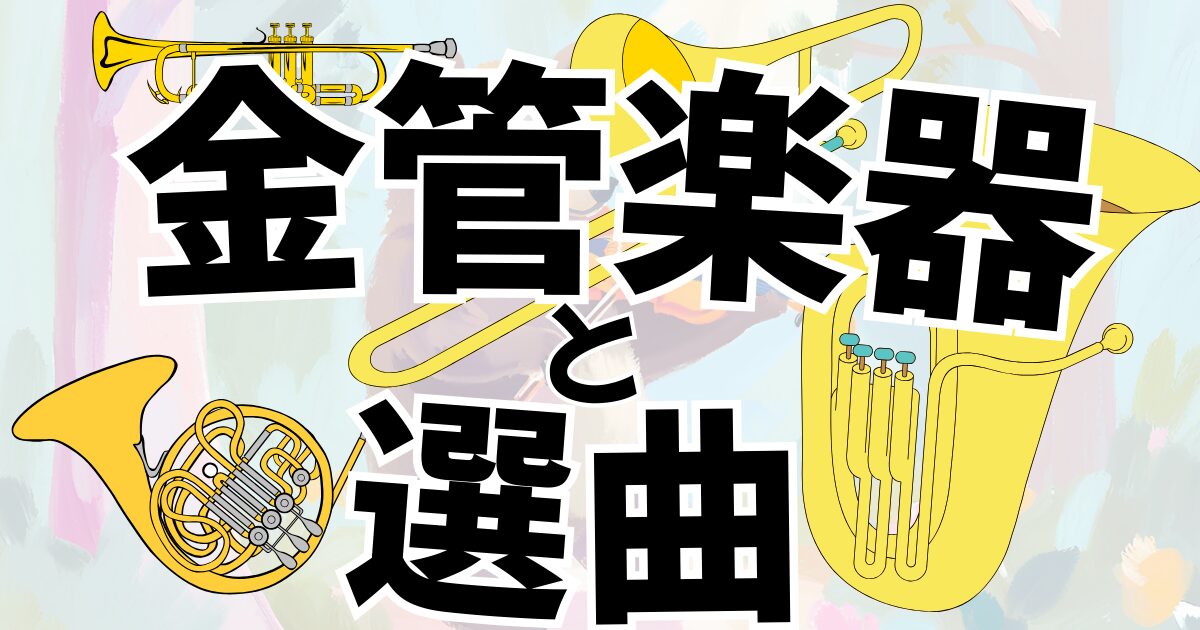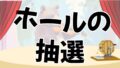アマチュアオーケストラにとって選曲は、演奏会成功のカギ。
でもその裏で、「金管の出番が少ない…」という声、上がっていませんか?
特に古典派の交響曲では、金管セクションの“待ち時間”が長く、モチベーションの維持が難しくなることも…。
この記事では、金管楽器の出番と団員のやりがいを両立させるための選曲やプログラム構成の工夫を、歴史的背景も交えて詳しく解説します。
なぜ不満が出る?アマチュアオーケストラならではの選曲事情
アマチュアオーケストラの選曲は、団員の構成や技術レベル、演奏会場の規模、指揮者の意向、そして団員の「やりたい曲」も大事な要素。
しかし曲によっては、金管楽器がほとんど出てこないことも…。
弦楽器は常に出番がありますが、金管は曲によって編成に大きな差があるため、「出番が少ない=モチベ低下」につながることもあります。

弦は「降り番」の感覚が無いから、つい忘れがち!
なぜ出番が少ない?金管楽器とオーケストラ〜歴史の話〜
🎺 バルブがなかった時代の金管楽器
産業革命以前、つまり18世紀末までの金管楽器には、現在のようなバルブ(ピストン・ロータリー)機構は存在していませんでした。
そのため、演奏できる音は自然倍音のみ。これを演奏するのが「ナチュラルトランペット」「ナチュラルホルン」と呼ばれる楽器です。
自然倍音とは?
自然倍音は、管の長さによって決まる一定の音列のことで、自由な旋律演奏には不向きです。音階の一部しか出せないため、曲中での使い方もかなり限定的でした。
🎺 オーケストラでの金管楽器の役割は「効果音」に近かった?
バロック時代や古典派初期の作品において、金管楽器の出番は限られており、基本的には「荘厳さ」「軍隊」「狩り」など、特定の情景や場面を象徴する効果音的な使われ方が主流でした。
- トランペットは華やかなファンファーレ的な使い方
- ホルンは「狩りのホルン」として自然の情景や田園風景の描写に使用
- トロンボーンは宗教音楽や劇音楽(オペラ)に限って登場(交響曲にはほぼ登場しない)
🎺 古典派初期のオーケストラ編成と金管
18世紀の古典派初期(ハイドンやモーツァルトの初期作品)では、オーケストラ編成は今よりずっと小規模でした。
基本的な編成は以下の通りです。
- 弦五部(1st・2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバス)
- 木管(フルート1〜2、オーボエ2、ファゴット2)
- 金管(ホルン2、トランペット2)※ない場合もある
- ティンパニ(トランペットとセットで扱われることが多い)

トランペットとティンパニが登場する=「祝祭的な作品」
🎺 バロック時代の金管とオーケストラ例
バロック時代(17世紀〜18世紀前半)には、「トランペット=高貴」「ホルン=狩猟の象徴」というイメージが定着しており、オーケストラでもその役割が反映されています。
- バッハ:ブランデンブルク協奏曲第2番(トランペットの高音技巧が有名)
- ヘンデル:水上の音楽(トランペットやホルンが儀礼的に使われている)
🎺 産業革命で何が変わったのか?
19世紀の産業革命を経て、金属加工技術が向上し、バルブ付きの楽器が登場。
これにより、金管楽器でも**クロマチックな旋律(半音階)**が自由に演奏できるようになりました。
後期ロマン派では、金管セクションは「サウンドの柱」として主役級の存在になります。
- バルブシステム(回転式・ピストン式)が発明され、音程を自由に変更可能に
- 精密で均一な金属加工によって音質の安定性が向上
- 大量生産によって価格が下がり、一般に普及
↓
その結果...
↓ - 作曲家が金管を積極的に使うようになる
- オーケストラの金管セクションが大規模化
- 金管の表現力が飛躍的に向上
金管が少ない曲 vs 多い曲 〜代表曲と編成比較〜
金管楽器の種類
ホルン、トランペット、トロンボーン、チューバ、バストロンボーン、サックス、ユーフォニウム、コルネット、ワグナーチューバなど

団員にチューバ奏者がいると曲探し大変かも…
金管楽器の出番が少ない代表的な古典曲
| ハイドン: 交響曲第94番 | モーツァルト: 交響曲第40番 | ベートーヴェン: 交響曲第7番 | |
|---|---|---|---|
| ホルン | 2 | 2 | 2 |
| トランペット | 2 | . | 2 |
金管が大活躍する大編成の曲
| ワーグナー: ニーベルングの指輪 | マーラー: 交響曲第8番 「千人の交響曲」 | シュトラウス: 「アルプス交響曲」 | |
|---|---|---|---|
| ホルン | 8 (4本はワグナー・チューバに持ち替え) | 8 (4本はワグナー・チューバに持ち替え)+12本(バンダ) | 8 |
| トランペット | 3 | 5 | 4+2 |
| トロンボーン | 3 | 4 | 4+2 |
| バストロンボーン | 1 | – | . |
| チューバ | 1 | 1 | 2 |

管が活躍する曲は、弦の演奏難易度が高いことも多いので注意!
金管の不満を解消!選曲・プログラムの工夫3選
工夫次第で金管楽器セクションも満足できるプログラム作りができます。
①: 古典派と、ロマン派や近現代曲を組み合わせる
前半:モーツァルト(古典派)
∔
後半:ドヴォルザーク、シベリウス(ロマン派、近代)
金管楽器が「前半は少し待機だけど、後半がっつり吹ける!」と納得しやすいです。
② : 序曲・ファンファーレを組み込む
- ワーグナー:ニュルンベルクのマイスタージンガー前奏曲
- ジョン・ウィリアムズ:オリンピック・ファンファーレとテーマ
金管楽器が主役になれる曲を加えると、バランスが良いです。
③ : 金管アンサンブルを取り入れる
- 開演前や休憩中に金管アンサンブルを演奏する
- アンコールで金管楽器中心の映画音楽や現代曲を取り入れる
出番がなくても「別枠で活躍できる!」と感じてもらえます。

金管楽器の編成が大きい曲は、ホール広さも必要!
まとめ|金管楽器のモチベーションも大切にした選曲を
アマチュアオーケストラの選曲では、団員の人数や演奏レベル、会場、予算など様々な条件がありますが、**「金管の出番が少ない問題」**は見落とされがちです。
- 古典派の曲は、ロマン派や近現代曲と組み合わせる
- 金管が活躍できる序曲やファンファーレを加える
- 金管アンサンブルなどプログラム外の演奏機会をつくる
選曲の工夫で、団員全体のモチベーションと演奏会の充実度はぐっと高まります。
金管も弦も、みんなが「やってよかった!」と思えるプログラムを目指しましょう。

オケの成長と団員のモチベ維持、両方叶う選曲を目指そう!