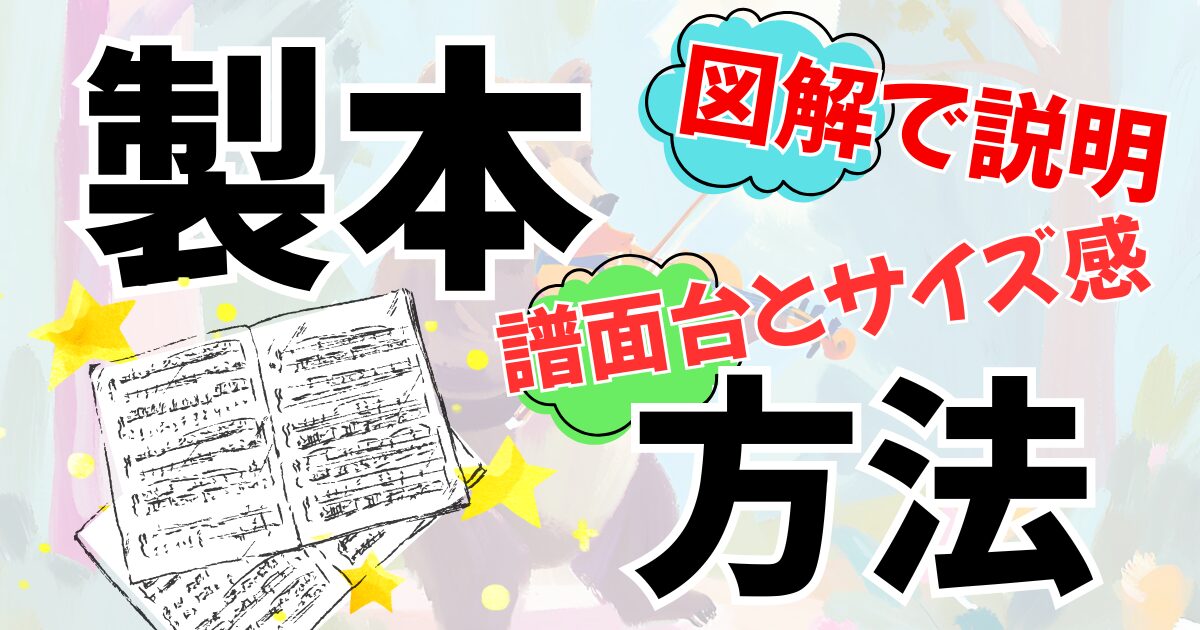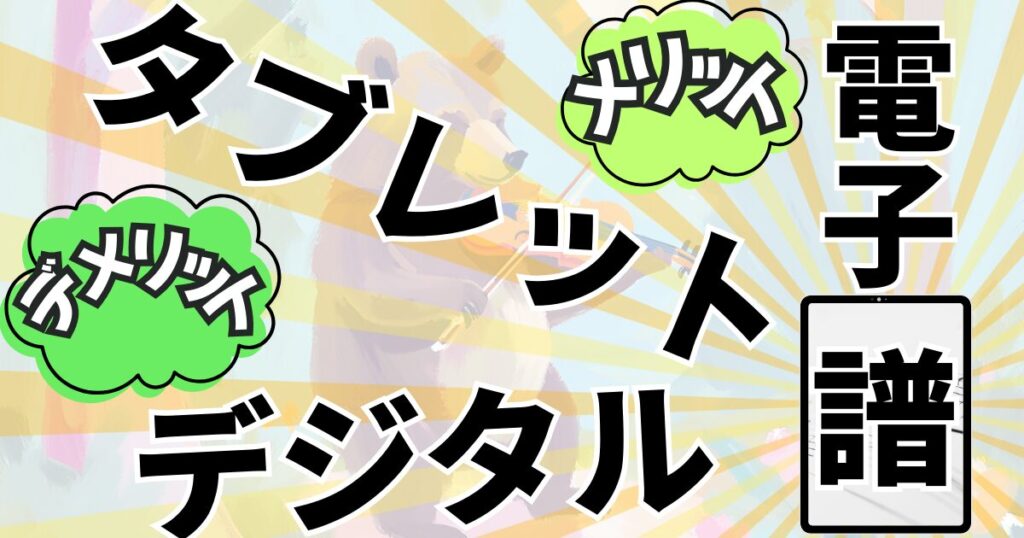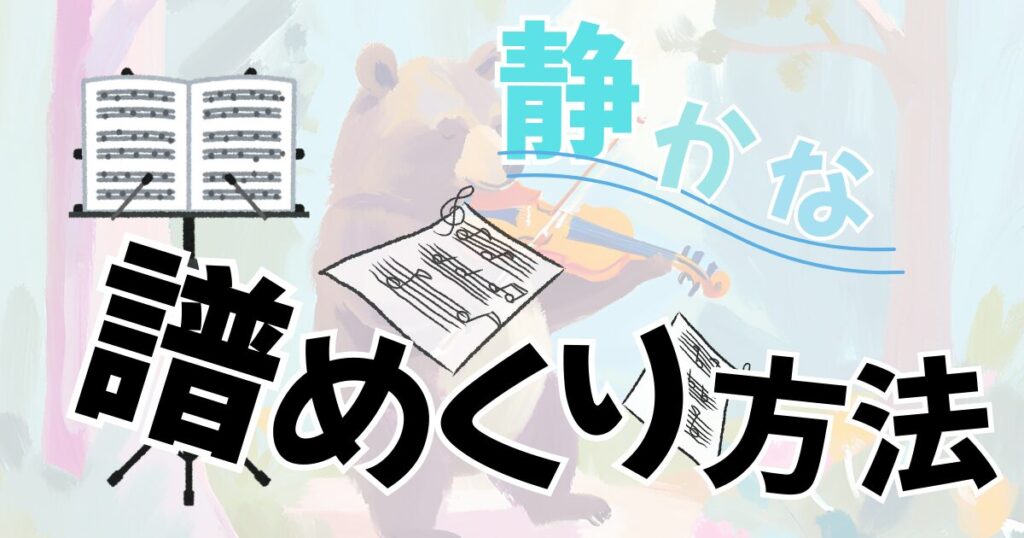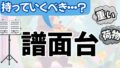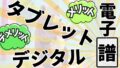良い演奏はきれいな製本から。
読みやすくて書き込みやすい楽譜を作るには?
譜面サイズの選び方や印刷方法、ズレにくい製本のコツを図解付きで解説します。
どのサイズで作ろうか迷っている方向け、比較のイメージ画も掲載!

製本を見ると、その人が分かると思う(持論)
- 譜面台上のサイズ感
- 片面印刷か両面印刷か
- 製本テープ、両面テープ、はさみ
- 「やま側」は製本テープか両面テープか
楽譜製本の流れ
① データDL、紙媒体入手
アマチュアオーケストラの楽譜データは、各自でDL(ダウンロード)することが一般的です。
一部複写ができない楽譜(著作権切れ前の曲など)は、紙媒体で配付されます。
- Googleドライブでのファイル共有
- PDFをメール添付で配付
- IMSLP( International Music Score Library Project)サイトからDL
- 紙媒体の配付
② 紙、サイズ選び
データ形式での配付の場合、用紙の種類とサイズを個人で選べることはメリットです。
白紙の照り返しが目にきついと感じる人は、オフホワイトの用紙がおすすめです。
譜面台に置いたときの安定感や書き込みやすさは、紙の厚さを選べば調整できます。
見開きのサイズは A4か B3がおすすめです。


タブレット譜についても考察したよ
③ プリントアウト
自宅やコンビニ、図書館などでプリントアウトします。オケ全パート分など大量に印刷する場合は、キンコーズやネット印刷サービスの利用もおすすめです。
サイズやも豊富で両面印刷でプリントアウトすると、製本過程で手間を省くことができます。
1ページを A4サイズで作る場合、 A3用紙に2ページ分横並び印刷すれば、印刷代が半分浮きます。
- データに「ページ抜け」や「反転」はないか?
- 用紙サイズは決めたか?
- <必要に応じて>拡大、縮小したか?
- <両面プリントの場合>両面になる2ページの組み合わせは正しいか?
④ 製本アイテム準備
| 製本テープ、マスキングテープ、紙テープ | 色:白 幅:15 mm前後(五線譜にかからない幅) 背表紙用に太めもあると良い(楽譜の厚さ次第) |
| 両面テープ (のりでもOK) | 幅:10 mm(裏に使うので何 mmでもOK) |
| はさみ | – |
| カッター、裁断機 (あるときれいに仕上がる) | 余白を切り落としてサイズを小さくするため 端のズレを切り落とすため |
- ニチバン:紙粘着テープ 幅12 mm(H210-12)
➢ ハサミが無くても手で切れやすい
➢ 色が白く譜面に馴染みやすい
➢ 背表紙用には18 mmがおすすめ

広い机で作業してね
⑤ 製本作業
演奏会まで数ヶ月は使うので、きれいに仕上げましょう。
本番譜であれば、同じプルトの人からも見やすくする必要があります。


端のズレや余分な余白は、裁断機で落とすときれいでコンパクト!

60枚まで裁断可能!楽譜係さんにおすすめ!
まとめ
製本は演奏会への第一歩です。
初回合奏までにちゃんと仕上げましょう。
オケ譜はを製本する場合は特に、自分だけでなく同じプルトの奏者にとっても、見やすく、書き込みやすく、めくりやすい仕上がりが必要です!
雑な製本は、演奏を邪魔する譜めくり音の原因にもなります。

「静かな譜めくり」記事も参考にしてね!