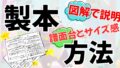オーケストラでの電子楽譜は本当に便利?
タブレット使用のメリット・デメリットを、管楽器・弦楽器の視点から詳しく解説。
演奏現場で起こりがちな問題や、使いこなすための工夫も紹介します。
- 管楽器奏者にはおすすめ
- プルト弾きの弦楽器奏者は、調整が必要
- 演奏時以外でも利用価値が大きい
オーケストラにおけるタブレット譜(電子楽譜)の活用とは?
アマチュアオーケストラでは、管楽器を中心にタブレットでのデジタル譜が増えています。
弦楽器でもソロや、カルテットなどの室内楽では見かけます。

「電子楽譜」「デジタル楽譜」「タブレット譜」呼び方の違い
「タブレットで表示させるデータ形式の楽譜」の名称は?
- 電子楽譜(電子譜)
- デジタル楽譜(デジタル譜)
- タブレット楽譜(タブレット譜)
1.電子楽譜が最も一般的のようです。ただ、色々なアプリやサービスで2.デジタル楽譜という名称も使われており、一本化はされていないようです。
3.タブレット楽譜は、文字数も多い上に略した際に「タブ譜(タブラチュア譜)」と混同しそうです。ただ、会話の中では「あれ?楽譜は?」「私、タブレットなんだ!」と一番使われている気がします。
タブレットで楽譜を見るメリット9選
1. 持ち運びやすい
複数の楽譜を一つのデバイスに保存できるため、重い楽譜やサイズの揃わない楽譜を何冊も持ち歩かなくて済みます。
また、楽譜や教本よりもサイズがコンパクトで、カバンにも入れやすいです。

教本なんて1冊中、1ページしか見なかったり
2. 管理・検索しやすい
曲名や作曲者名で並び替えたり、演奏会ごとにフォルダを作ることができます。
クラウドストレージを利用すれば、容量の心配なく大量の譜面を管理できます。
3. 書き込み・編集しやすい
スタイラスペンがあれば譜面への書き込みも可能で、ワンタップでフォントサイズ変更、ハイライト、消去機能が使え、筆記用具よりも編集が簡単です。
4. 譜めくりが効率的
スワイプやジェスチャー、フットペダルで譜めくりができるため、演奏を中断しないで済みます。(アプリ登録が必要な場合があります)
5. 見やすい
調光が可能なため、オーケストラピットなどの暗い場所でも見やすいです。
ズーム機能を使って譜面を拡大・縮小できるのも、タブレットならではです。
6. 収納スペースの削減
楽譜を収納するスペースも必要なくなります。タブレット内のデータが増えてきたら、USBやSDカードなどの外部メモリや、クラウド、パソコンへのデータ移動をするだけなので、本棚を増やす必要もありません。
7. 製本コスト・手間の削減
印刷や製本が不要なので、コストや手間が削減できます。演奏会終了後の楽譜の処理も簡単です。
ただ、楽譜が紙媒体での配付だった場合、デジタル化の手間がかかります。

すぐに練習が始められるね
8. 風の影響を受けにくい
室内の空調や屋外演奏で悩まされがちな風への耐性もあり、譜面がふわつきません。
9. 楽譜の共有が簡単
データをクラウドに上げれば、複数デバイス(複数人)で楽譜を表示させたり、編集したりすることができます。
電子楽譜のデメリットと注意点
1. バッテリーの持続性
バッテリーが切れるとタブレットが使用できなくなるため、長時間の演奏では残量に注意が必要です。
2. 眼精疲労
長時間タブレットの画面を見続けると、目に負担がかかることがあります。
スポットライトの下では画面の反射が強い場合もあり、注意が必要です。
3. 画面が小さい
タブレットのサイズが小さい場合、譜面が見にくくなることがあります。
紙の楽譜のように見開き2ページを表示させることが難しく、できたとしても表示が小さくなり、弦楽器の譜面だとほとんど見えません。
特にプルト弾きする場合は、よほど視力の良い奏者でないと難しいです。

「D.C.」「D.S.」「リピート」とか、事前にめくる練習が必要!
4. デバイスの脆弱性
タブレットは、落下による故障や予期せぬ不具合のリスクがあります。
5. 操作習得のハードル
機能的に使用するためには、タブレットやアプリの操作に慣れる必要があります。
6. プルト弾きでは調整が必要
プルト弾きの弦楽器では、ななめから画面を見ることになります。
画面の反射や譜面の小ささなど、見やすさの調整が必要のため、使用の可否を確認しなければなりません。
7. 初期投資が必要
タブレット本体やフットペダル、スタイラスペンなどの周辺機器の購入が必要です。
iPad の13インチであれば130,000円程度。
フットペダルとスタイラスペンを追加すると150,000円はかかります。
周辺機器:フットペダルのおすすめ
iRig BlueTurn(IK MULTIMEDIA)〔フット・ペダル〕
➢ イタリアの音楽制作ソフトウェアおよびハードウェアの開発メーカー
➢ Bluetooth(Android / iOS / Mac対応)
➢ 静音で動作
➢ バックライト付き

本番で使用するなら、信頼できるメーカーの商品をすすめるよ!
オンライン楽譜サービス例:ヤマハ「ぷりんと楽譜」
楽譜をオンラインでダウンロードできるサービスがあります。
「ぷりんと楽譜」は、ヤマハの毎月定額(サブスク)型サービスで、アプリをダウンロードしたタブレットやスマホで、楽譜を探したり、ダウンロード・印刷することができます。
ピアノだけでなくヴァイオリンやギターなど、様々な楽器の楽譜が豊富です。
- 楽器店に行かなくても楽譜が探せる
- 24時間いつでも楽譜が買える
- クラシックやポップス、ジブリ、アニメなど28万点以上
- 1曲から買える
オンライン楽譜サービスの例
ダウンロード形式なので、プリンターで印刷すれば紙の楽譜にもできます。

| プラン名 | 月額料金(税込) | アプリ閲覧数 | PDF割引 |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 990円 | すべて見放題 | ダウンロード半額 |
| ライト | 480円 | 月5点まで | ダウンロード半額 |
まとめ
「電子楽譜は便利!でも、用途や楽器に応じた工夫が必要」
携帯しやすく、楽譜の管理・共有のしやすさがある一方で、バッテリーや画面表示に限りがあり、初期投資額も必要です。
オケの弦楽器奏者が使うには、2ページ見開き表示が難しい点と、画面の角度の点でハードルが高めです。