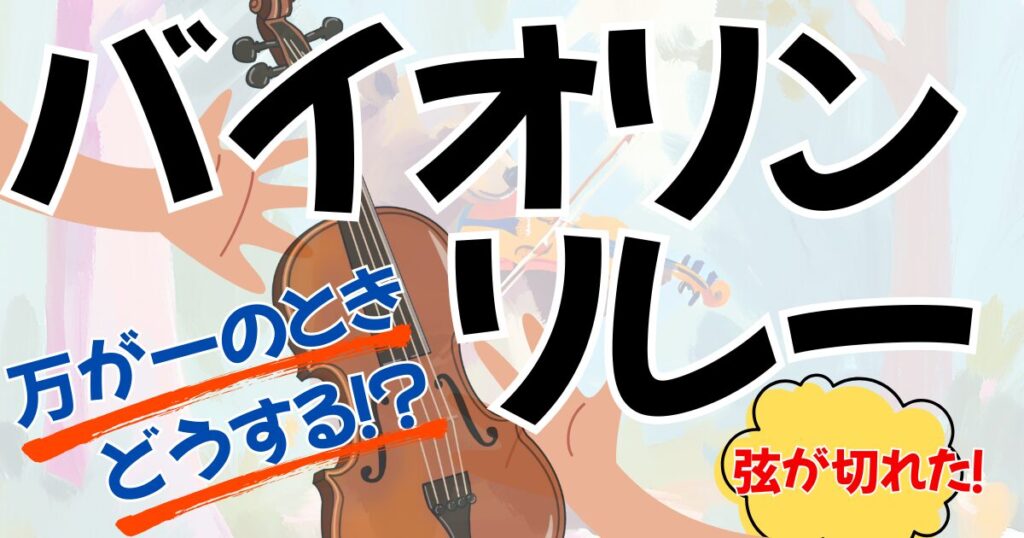どんなにコンディションを整えても、演奏中に弦が切れる、楽器が壊れる…そんなアクシデントは起こるもの。
そんな「まさかの瞬間」に、オーケストラの対応力が試されます。
この記事では、演奏中のトラブルに備える“予備楽器”の重要性と運用方法について解説します。
オーケストラの「危機管理力」や「対応力」が問われる場面です。

くまリン
メリット、デメリットをまとめたよ
予備楽器ってなに?
🎻 予備楽器ってなに?
予備楽器とは、本番中のアクシデントに備えてステージ上に置かれる替えの楽器のこと。
本番中に弦が切れた時は、予備楽器と交換して演奏を続けます。
チェロやコントラバスなどの低弦楽器は、スペースやコストの問題から、ステージ上に予備楽器が用意されることはありません。
🎻 予備楽器は誰の楽器?
- オーケストラ所有の楽器
- 団員のサブ楽器
- ソリストのサブ楽器
いずれの楽器も、演奏できる状態にメンテナンス・チューニング済みであることが大前提です。
ヴァイオリン協奏曲の場合、ソリストが自身のサブ楽器を傍らにスタンバイさせることもあります。
🎻 どこに置くの?
- 舞台上の一番後ろのプルト近くに設置するのが一般的。
- 椅子に寝かせるか、スタンドに立てる。
- 舞台が狭い場合は、舞台袖に控えさせることも。
- ソリストの予備楽器は、ソリストの近く(ヴァイオリン1プルトの前)に置かれる。

くまリン
存在に気付かないお客様も多いよ
🎻 予備楽器のメリット
- 影響が最小限:
ステージ上でトラブル対応が完了するため、労力や時間が最小限で済みます。
奏者のイレギュラーな出入りがないため、曲への影響も抑えられます。 - 安心感:
予備楽器があることで安心感が生まれ、パフォーマンスに集中しやすくなります。

くまリン
予備楽器がない場合は、弦を張り替えるために下がらなきゃいけないからね
🎻 予備楽器のデメリット
- スペースが必要:
予備楽器を舞台上に置く場合、椅子1脚または楽器スタンド分のスペースが必要です。
ステージ上に置けない場合は、舞台袖にスタンバイも◎。 - 管理が必要:
弾ける状態にメンテナンスが必要です。
演奏会当日、予備楽器1本分の荷物が増えます。 - コストがかかる:
予備楽器として貸し出すためにメンテナンス費用が掛かることもあります。
🎻 予備楽器の運用手順
- 舞台のスペースを確認する
➢ 椅子置きか?スタンド置きか? - 使用可能な楽器を探す
➢ できるだけ状態の良い楽器を
➢ メンテナンスに掛かる費用は経費にすると◎ - 本番前にチューニング&設置する
➢ 担当者を決めておく - 終演後に回収
➢ 担当者を決めておく
🎻 予備楽器が用意できない場合は?
予備楽器を用意しているオケは決して多くはなく、楽器のトラブル対応は「バイオリンリレー」が使われることのほうが一般的です。

くまリン
「バイオリンリレー」についても解説中!
まとめ
予備楽器は、「使わずに済む」のが理想です。
でも、“ある”というだけで、演奏者の集中力・安心感・舞台のスムーズな進行に、陰ながら貢献してくれます。
スペースやコストの許す範囲で導入を検討をおすすめします。